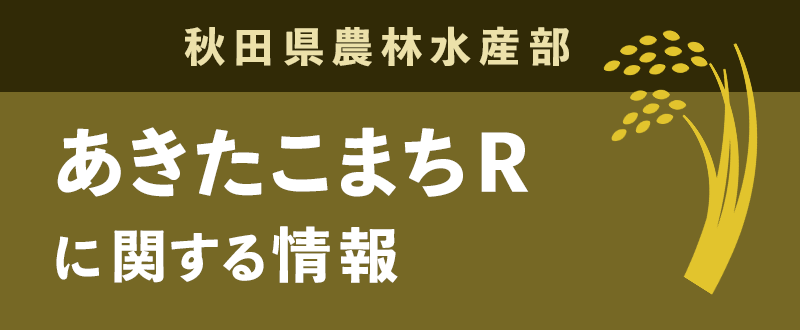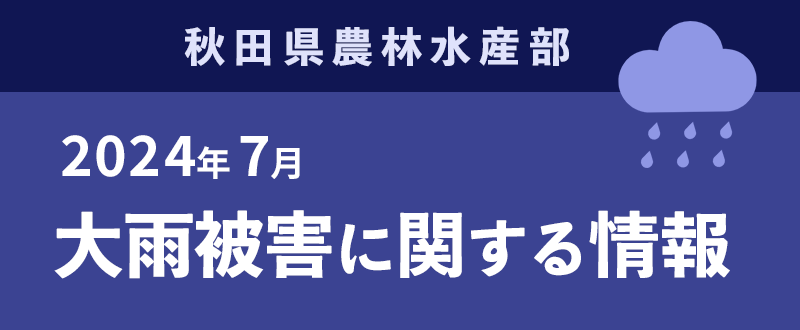そばの力で農村集落を次世代へつなぐ~横岡稲倉そば生産組合~
ふるさと秋田農林水産大賞の受賞者の業績を紹介します。
令和3年度ふるさと秋田農林水産大賞(農山漁村活性化部門) 横岡稲倉そば生産組合
1 経営発展の経過
●平成23年
中山間地であるにかほ市象潟町横岡地区では、耕作放棄地の増加が懸念されていたことから、その解消とそばの生産振興を目的に、「稲倉そば生産組合」を設立した。
はじめは、齋藤組合長と妻のかおる氏が主体となって耕作放棄地の所有者を一軒一軒訪ね、地道にほ場を集積した。
設立当初の平成23~26年は、コンバイン1台を使用し、4名で計6㏊のそばを作付けした。

●平成27年
地区名の「横岡」と、昔からある農地を守り、維持したいという組合の思いから、名称を「横岡稲倉そば生産組合」に改称した。この頃からコンバインを2台に増やし、10名で計33.1㏊のそばを作付けした。
●平成29年
コンバインを3台に増やし、11名で計52.1㏊のそばを作付けした。また、乾燥調製施設を新たに建設し、収穫以降の作業も含め、丁寧でこだわり抜いた生産を行うようになった。
●令和2年
そば作付面積が65.1㏊に拡大したことから、効率的な農業経営の実現に向けて機械導入を図るとともに、横岡地区における更なる農用地の利用集積も積極的に行った。
●令和3年
そば作付面積は計78㏊まで拡大し、にかほ市全体で作付されている夏そば・秋そばを合わせた約350㏊のうち、約22%を占めるに至った。
そば栽培に適さない水はけの悪い農地が多い中でも、安定して高収量の生産を実現している技術が評価され、第32回全国そば優良生産表彰事業において、「一般社団法人日本蕎麦協会会長賞」を受賞した。
高齢化に伴い農地を手放す農家が増加しているが、そばの大規模生産のパイオニアとして、地域内外から注目を集めている。
●令和4年以降
横岡地区内において、地区内農用地の2/3以上を当組合で利用集積することを目標とし、農地の集積を意識した営農管理に努めていく。

2 活動内容
(1)耕作放棄地の活用
横岡地区の農地を守り、保全していくため、耕作放棄地を積極的に引き受け、そばを作付けしている。
組合の熱意が地域でも受け入れられており、近年では農地所有者側から「使って欲しい」と声をかけられることも多い。
地域の高速道路の入口付近は耕作放棄地が多く、景観が悪かったため、当組合主導の下、木の伐採・抜根を行い畑を造成し、そば栽培を始めた。
組合が根気強く管理作業を続けた結果、今では多くのそばが作付けされるに至り、開花時期にはそばの白い花が一面に咲き誇り、豊かな景観を生み出している。

(2)「そば打ち体験」の実施
当組合では、「地元産のそばを味わってもらうことで、地域の環境やそば栽培に興味を持って欲しい」という願いから、そば打ちを通した食育の推進に取り組み、地域活性化に力を入れてきた。
そば打ち体験では、組合で所有する石臼を使って、横岡産のそばの実を挽いてそば粉にし、そば粉100%に、卵、豆腐をつなぎとして加えた十割蕎麦を作ることをこだわりとしている。
当組合では、そば打ち体験の講師を毎年引き受けており、「そば打ちが楽しかった」「非常においしかった」と、小学生から高齢者まで幅広い年代の参加者から、高い評価を得ており、地域の新たな文化として根付き始めている。
また、旧象潟町を中心に活動する地域おこし協力隊員ともそば打ちを通した交流を行っており、関係人口を増やしながら、活動の幅を広げている。

(3)飲食店への提供
東京都内で毎年開催される新そば祭に、平成28年からそばを提供しており、県外にも秋田県産そばを積極的にPRしている。
清涼感のある香りと味わいが特徴の横岡産そばは、消費者からの評価が高く、リピーターも獲得しており、今後も取組を継続していく。
※新そば祭は、8月初旬頃から東急線沿線の飲食店「しぶそば」が行う企画で、夏そばの収穫期が早い当組合の特色を活かし、全国に先駆けて新そばを提供している。
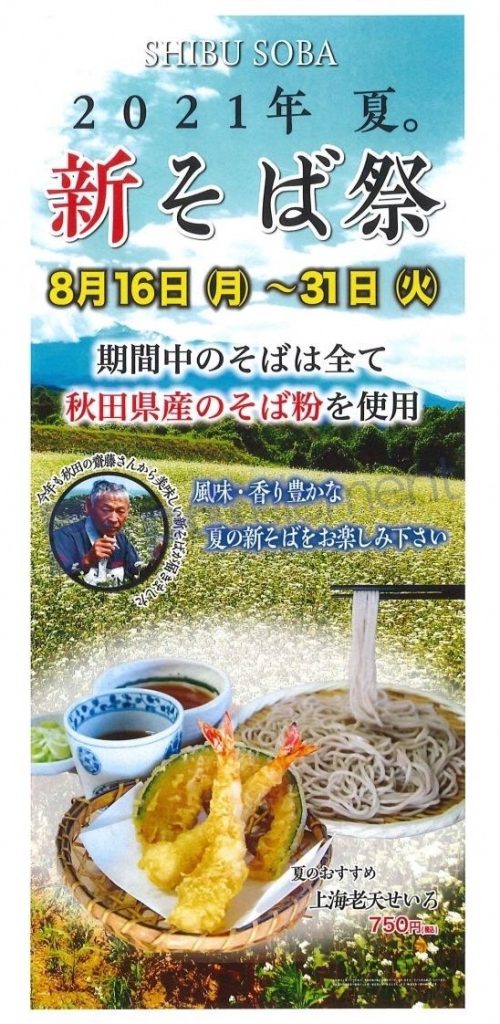
3 地域農業、地域社会に及ぼした影響
(1)地域に先駆けた高度な栽培技術
①徹底した排水対策
横岡地区は、耕作放棄地や水田転作地が多いため、根気強い排水対策が必要である。
このため組合では、深さ50~60cmの明渠及び弾丸暗渠の施工を3年ごとに行い、継続して排水対策の徹底に取り組んでいる。
②土壌診断に基づく施肥
常に多収を目指し、栽培に最適な土壌条件になるよう定期的に土壌診断を行っており、診断結果に基づいて、ほ場ごとに石灰や元肥を調整し、生育量を確保している。
③適期播種を可能とする作業の効率化
播種後の降雨による湿害を避けるため、天気予報に基づいて播種好適日を判断するとともに、施肥、耕起、播種の作業を同時に実施できるよう機械化している。作業効率が著しく向上し、所要時間短縮が図られており、適期を逃さずに播種を行っている。

④適期刈り取り
黒化率70%という実需者の要望に応えるため、適期の刈り取りに努めており、ほ場ごとに成熟期を見極めながら、作付面積に合わせてコンバイン稼働台数を増やして対応している。
こうした工夫により、当組合では市の平均を超える高単収を例年達成しており、令和3年の夏そばと秋そばの平均単収は、当組合で50kg/10aと、市全体の平均39kg/10aを上回っている。
⑤乾燥調製
そばの温度が上がり過ぎないように、送風温度を30℃以下として小まめに調整しており、水分含量に応じて通風乾燥を丁寧に行い、高品質なそばに仕上げている。
(2)地域の模範となる効率的な作業体系・作付体系
①機械化の推進
耕作放棄地を活用した規模拡大への意欲が高く、作付面積の増加に合わせて機械の稼働台数を増やし、作業時間の短縮や作業効率の向上を図っている。

②作付体系の工夫
気象の影響を受けやすいそばの欠点を補うため、夏そばと秋そばを組み合わせた作付体系としており、湿害や病害、台風等による減収リスクを分散し、安定した生産を実現している。
(3)そば打ちを通した食育活動による地域活性化
①食育の推進
毎年12月29日に当組合主催の「そば打ち体験」を開催しており、会場の横岡自治会館には例年100名以上の参加者が集まっている。
リピーターも多く、4年連続の参加者もいるほど人気を博しており、令和2年度からは、参集範囲をにかほ市全体に拡大し、より多くの人が横岡産そばを認識し、高い関心を持ってくれるよう取組を強化している。

今年度は、新型コロナウイルス感染症対策を徹底し、午前・午後各10組に限定して実施した。
また、地域の小学校や町内会等からの依頼で開催しているそば打ち体験には毎年多数の参加者が集まっているほか、市の婚活イベント等交流事業への協力依頼があるなど、地域での交流を生み出す一つのツールとなっている。
②グリーン・ツーリズムへの参画
平成22年からグリーン・ツーリズムにも取り組んでおり、毎年8月に東京都港区の子供達約20名を横岡地区に招き、横岡自治会と協力して農泊を受け入れている。
2泊3日の農業体験では、大根の播種や野菜の収穫、そば打ち等を通して農村交流を行っている。
新型コロナウイルス感染症拡大の影響で令和元年以降は受け入れを中止しているが、社会情勢を注視しながら、再開に向けた検討を進めている。
③次世代の担い手育成
齋藤組合長は、由利地域そば生産者協議会長も務めており、現地研修会を毎年開催し、地域一帯で栽培技術向上や担い手の育成及び掘り起こしに力を入れている。
また、そば打ちを通した食育活動を次世代へ引き継ぐため、若い農業者へのそば打ち指導等にも取り組んでいる。

お問合せ先
| お問合せ先 | 秋田県 農林水産部 農林政策課 企画・広報チーム |
| 住所 | 〒010-8570 秋田県秋田市山王4丁目1番1号 |
| メールアドレス | info@e-komachi.jp |
| 電話番号 | 018-860-1723 |
| FAX番号 | 018-860-3842 |