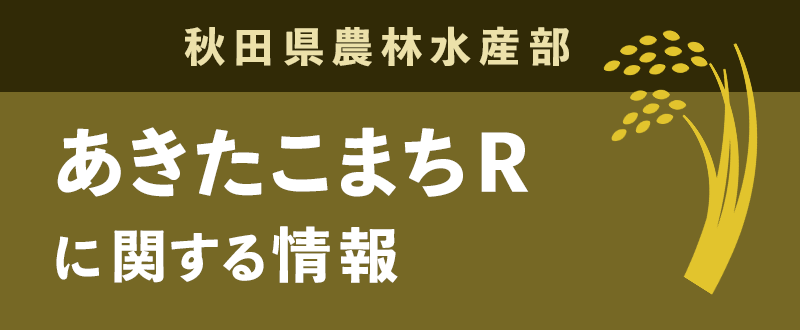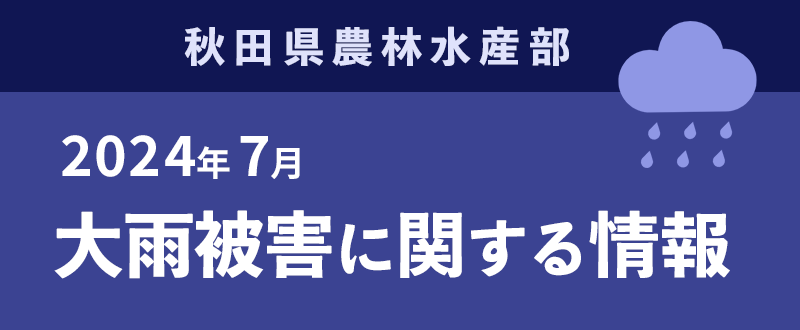なると餅
技術提供者:高橋イト子/大仙市(角館地区)

角館地域の「なるともち」は、農家の手作り菓子として利用されるほか、数件の菓子屋が角館名物として販売しています。
今は道明寺粉でつくられるようになりましたが、江戸時代には原料が粟だったため、阿波の鳴門にちなみ「なると餅」と名づけられたと言われています。
材料および分量
| 道明寺粉(粗挽き粉) | 1カップ |
| ねりあん | 250グラム |
| ぬるま湯 | 1カップ(200cc) |
| 笹の葉 | 5枚 |
| 食用黄色 | 少々 |
作り方
- 道明寺粉1カップにぬるま湯1カップを入れ、30分くらいおく。
- 1を30グラムずつに分け、ねりあん25グラムにまるめたものを中に入れてまるめる。
- なると型2を形を整え、上に黄色をつける。
- 3を蒸気の上がった蒸し器に入れて3分程度蒸す。
- 蒸し上がった餅を笹の葉にのせて出来上がり。
※道明寺粉とは、蒸したもち米を乾燥させて粗くひいたものです。